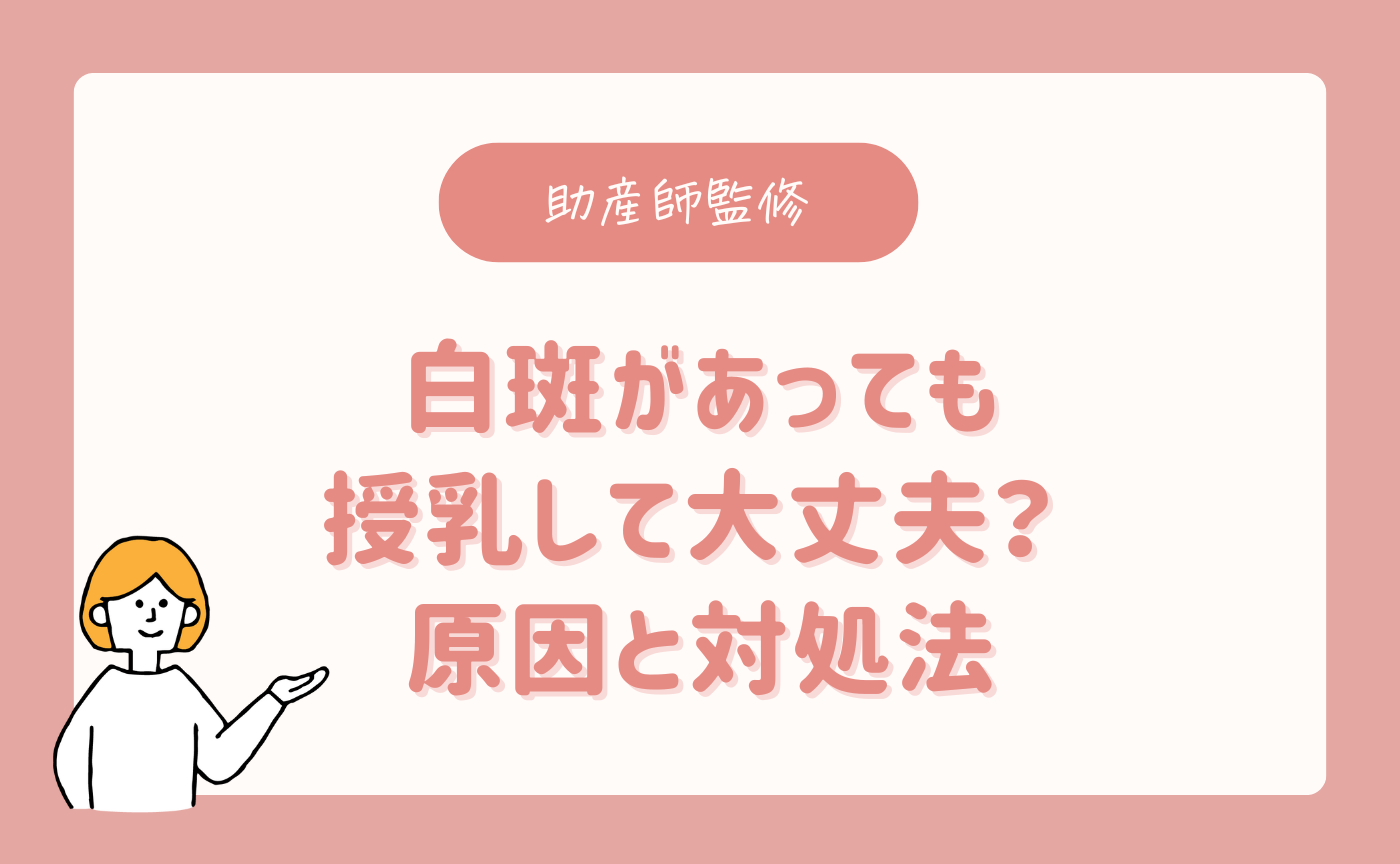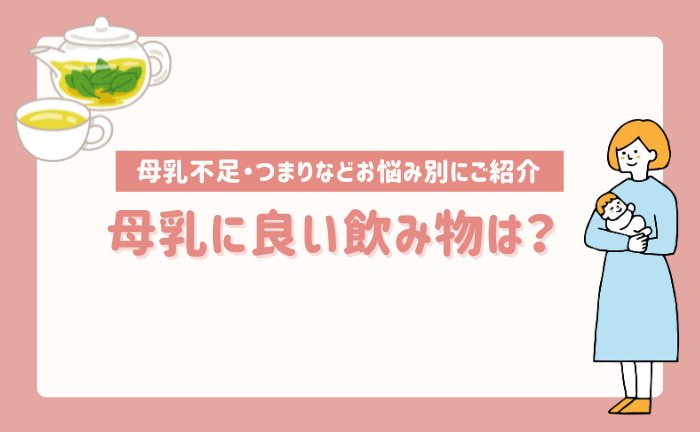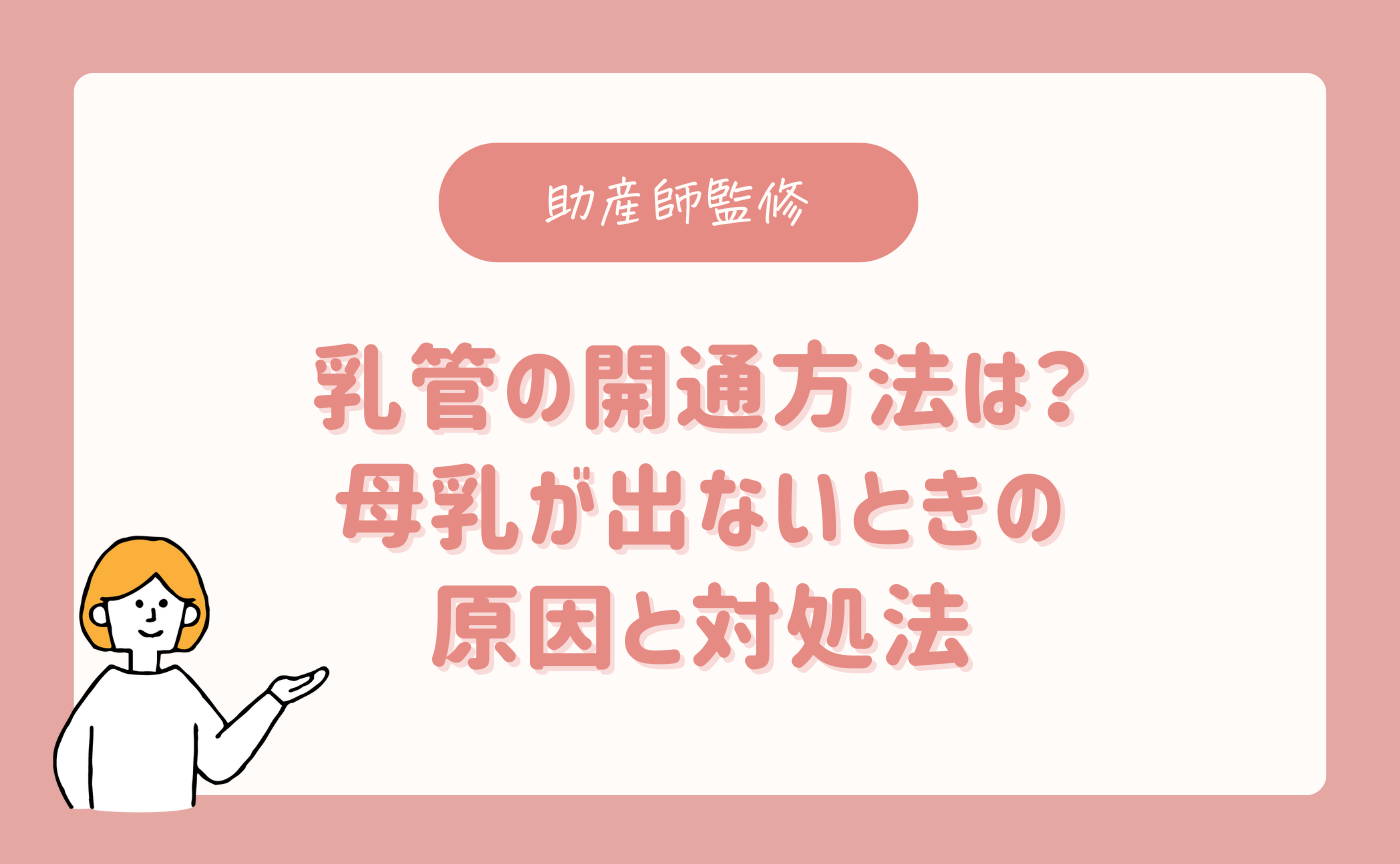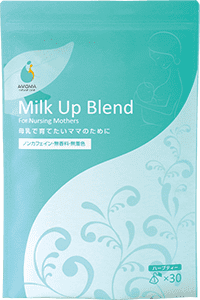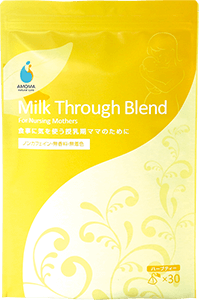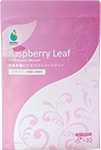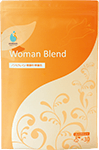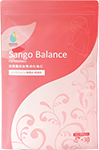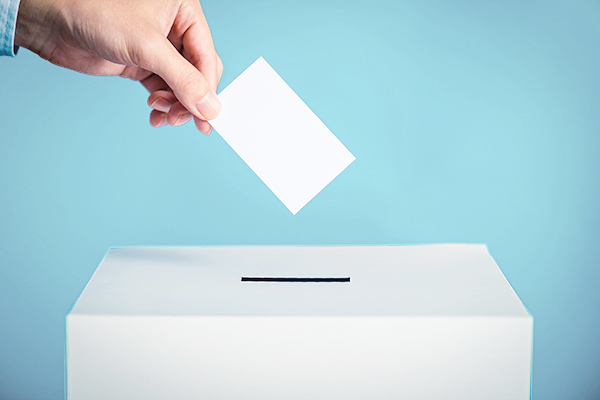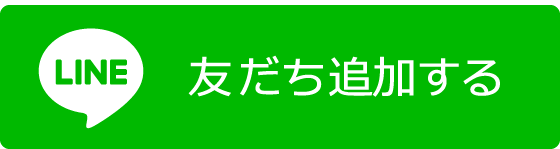【助産師監修】生後9ヶ月の赤ちゃん~離乳食や生活の様子~
2017.06.06

Mei Kamo
Mama writer
2013年2月生まれの男の子のママです。おしゃべりな息子と同じくおしゃべりなパパと3人でにぎやかに暮らしています。大好きなアーティストさんの音楽や大好きなDisneyを聞きながら、毎日楽しく育児に奮闘中です☆

浅井貴子
助産師
新生児訪問指導歴約20年以上キャリアを持つ助産師。毎月30件、年間400件近い新生児訪問を行い、出産直後から3歳児の育児アドバイスや母乳育児指導を実施。
タグをみる
生まれたばかりの頃はねんねばかりだった赤ちゃんも9ヶ月を迎える頃には、はいはいが上手になり、好きなところへ自分で移動できるようになる子が増えてきますね。
ママはそんな赤ちゃんの成長をひしひしと感じている頃だと思います。今回は生後9ヶ月の赤ちゃんに関する基本情報とよくある悩みをアドバイスとともに紹介します。
生後9ヶ月の赤ちゃん、体の様子

つかまり立ちをはじめる赤ちゃんも
生後9ヶ月の赤ちゃんの平均体重は男の子が7.2~10.7㎏、女の子が6.7~10.0㎏です。はいはいが上手になり、自分の行きたいところへ移動するのが早くなってきます。
中にはつかまり立ちを始める赤ちゃんもいるかもしれませんね。
また指の使い方も上手になり、小さなものでも親指と人差し指でつまめるようになります。
ママや家族はボタンや電池など赤ちゃんが口に入れると危険なものを手の届くところに置かないように注意しましょう。
9ヶ月の赤ちゃんの離乳食は?

食べる意欲が見られたら1日3回に
9ヶ月になると赤ちゃんも離乳食にだいぶ慣れてくる頃だと思います。
もぐもぐ動かすのが上手になった、手づかみで食べるようになった、バナナくらいの硬さのものを歯ぐきでつぶせるようになった、など食べる意欲が見られたら3回食に増やしていきましょう。
1回当たりの目安(9~11ヶ月)
・炭水化物(主食):5倍がゆ80~90g
・タンパク質(主菜):魚・肉15gまたは豆腐45gまたは卵1/2個または乳製品80g
・ビタミン類(副菜):野菜・果物30~40g
上記の量を参考に、子ども用お茶碗1杯弱から少しずつ増やしていきます。
赤ちゃんに大人が食事をしている様子を見せてあげることも大切なので、大人と同じ時間に 離乳食をあげるようにすると良いですよ。
おすすめレシピのご紹介
「豆腐ハンバーグ」
<材料>
豚赤身ひき肉10g、木綿豆腐3㎝角1個
<作り方>
ひき肉と水切りした豆腐を混ぜて、捏ねて、サラダ油少々をひいたフライパンで両面をしっかり焼いたら出来上がり!
豆腐のおかげでふわふわ触感なので赤ちゃんにも食べやすいです。
「おいもごはん」
<材料>
5倍がゆまたは軟飯(適宜)、さつまいも5㎜角(適宜)、黒すりゴマ少々
<作り方>
さつまいもを茹でて水切りし、さつまいもが潰れないようにごはんと混ぜる。黒ゴマをふったら出来上がり!
さつまいもを角切りにすることで噛む練習になります。
3回食になると、授乳よりも離乳食からとる栄養の方が多くなりますが、離乳食の後は欲しがるだけ授乳してあげましょう。
母乳育児でおっぱいの出が気になる場合はおっぱいの出をサポートしてくれるハーブティーがおすすめです。
疲れた時のリラックスタイムにもなりますよ。
生後9ヶ月の赤ちゃんの生活リズム

まねっこ遊びが大好き!
9ヶ月になると赤ちゃんもだんだん言葉の意味を理解し始めます。
声かけに反応するようになり、ママがしぐさを見せながら声かけすることで、言葉としぐさがつながり赤ちゃんもまねをするようになります。
「バイバイ」や「パチパチ」など、よくする行動をまねするだけで赤ちゃんはとても楽しいので、大好きなママが一緒にやってあげるとたくさんの笑顔を見せてくれることでしょう。
夜泣きがひどい場合は一度起こしてみても
9ヶ月の赤ちゃんは昼夜の区別がつき、朝まで眠る赤ちゃんが増えてきます。しかし毎日のように夜泣きをする赤ちゃんも少なくありません。
いろいろと夜泣き対策をしてもなかなか泣き止まない赤ちゃんに、困っているママもいるかもしれませんね。
そんな時は思い切って起こしてみるのもひとつの方法です。気持ちを落ち着かせて添い寝してあげると、ママのぬくもりを感じて赤ちゃんも安心しますよ。
寝室にアロマを焚くのもおすすめです。ママも一緒にリラックスして眠れるのではないでしょうか。
生活リズムがずれてきたら朝日を浴びる
離乳食が3回食になってくると、慣れるまでは時間がかかってしまい、夕飯・お風呂・就寝が遅くなることもあるかもしれません。寝るのが遅くなると朝起きるのも遅くなりますね。
すると毎日のリズムが少しずつずれてきてしまうことが考えられます。生活リズムがずれていると感じたら、朝起こす時に朝日を浴びさせてあげましょう。
そうすると体内時計が出来て早寝早起きのサイクルに戻りやすくなりますよ。
関連記事
■体の悩み
-
 【医師監修】乳腺炎で発熱!病院に行くべき?症状・原因・対処法も詳しく解説2024.10.08
【医師監修】乳腺炎で発熱!病院に行くべき?症状・原因・対処法も詳しく解説2024.10.08 -
 【助産師監修】白斑があっても、授乳して大丈夫? 取り方などを紹介2024.10.08
【助産師監修】白斑があっても、授乳して大丈夫? 取り方などを紹介2024.10.08 -
 【助産師監修】生後1・2・3ヶ月ごとの授乳間隔・授乳回数の目安は?2024.09.17
【助産師監修】生後1・2・3ヶ月ごとの授乳間隔・授乳回数の目安は?2024.09.17
カテゴリーランキング
AMOMAコラムについて
妊娠、出産前後はママにとっては初めてのことばかり。「これってあってるのかな?」 「大丈夫かな?」と不安や疑問に思った時につい手に取りたくなるような情報をお届けしたいと考えています。そのため多くの情報は助産師をはじめ専門家の方々に監修。テーマから読めるようになっていますので、ぜひ気になるものから読んでみてください。あなたの不安や疑問が解決できるお手伝いになれば嬉しいです。
AMOMAのパートナー

看護師、助産師、IFAアロマセラピスト、JMHAメディカルハーバリスト、NCA日本コンディショニング協会認定トレーナー
母乳育児、新生児~幼児にかけての育児相談全般、アロマやハーブを使用した産前、産後ケア 代替療法全般

管理栄養士・幼児食アドバイザー
メンタルヘルス食カウンセリング、子供の心を育てる食育講座、企業向け健康経営セミナーなど

日本神経言語心理家族療法協会公認家族心理カウンセラー、NLPファミリーセラピー・マスタープラクティショナー、子どものこころのコーチング協会インストラクタ
心理カウンセラー

日本産婦人科学会会員その認定医、産婦人科専門医、日本ソフフロロジ学会会員、東京オペグループ会員、日本アロマテラピー学会会員
産婦人科医
その他のお問い合わせはこちらから
 メールで問い合わせ
メールで問い合わせ






 amoma_naturalcare
amoma_naturalcare