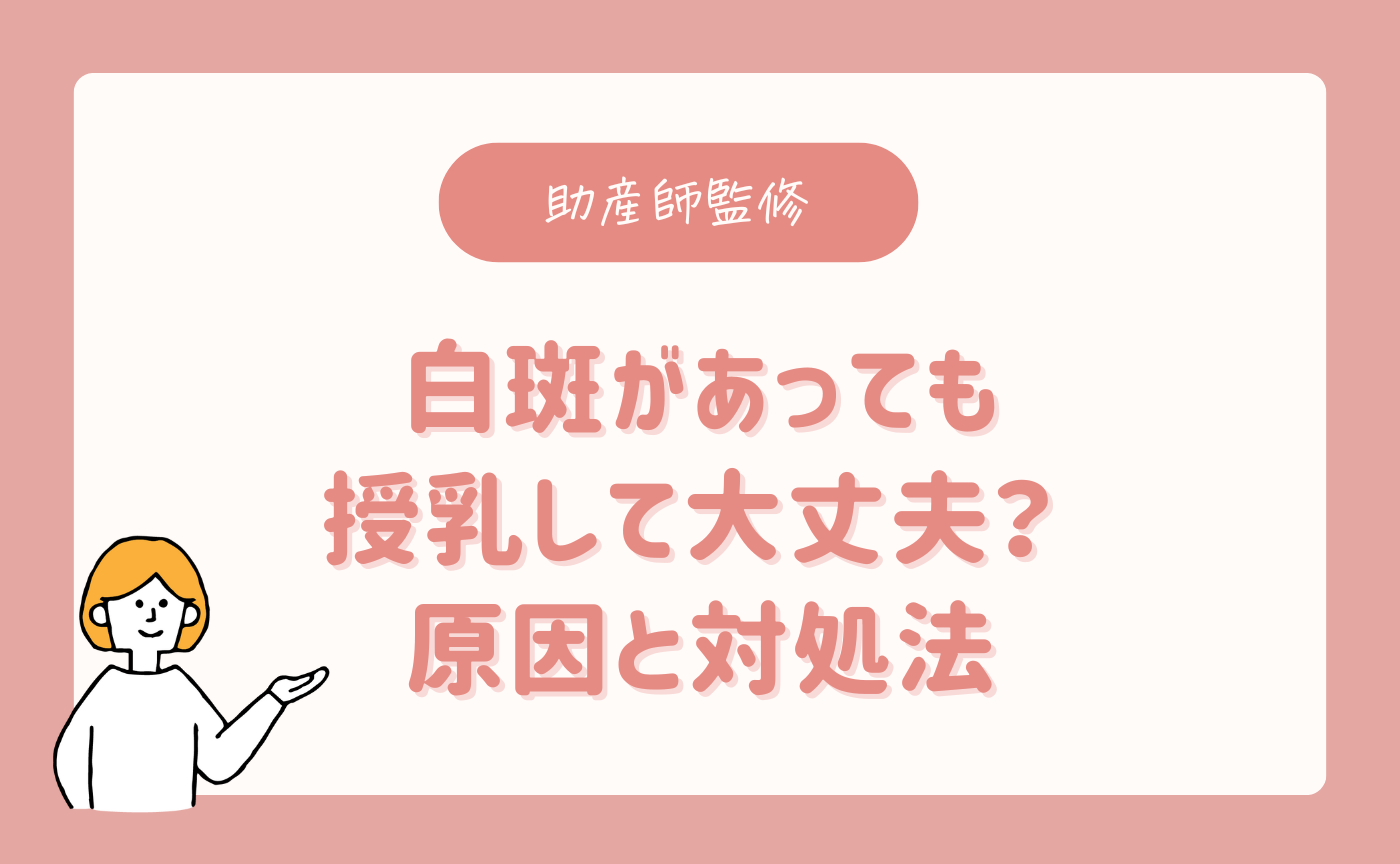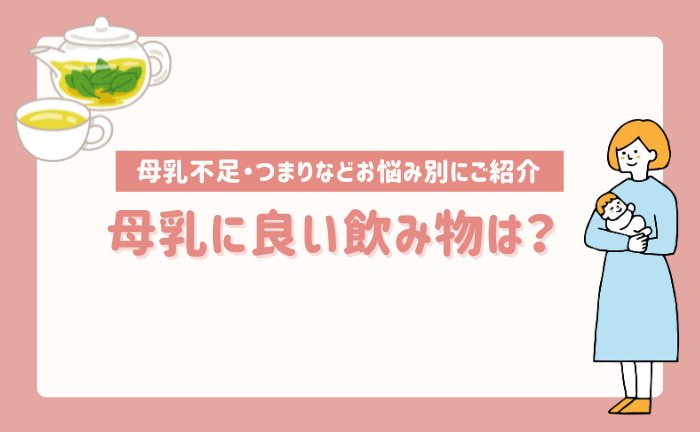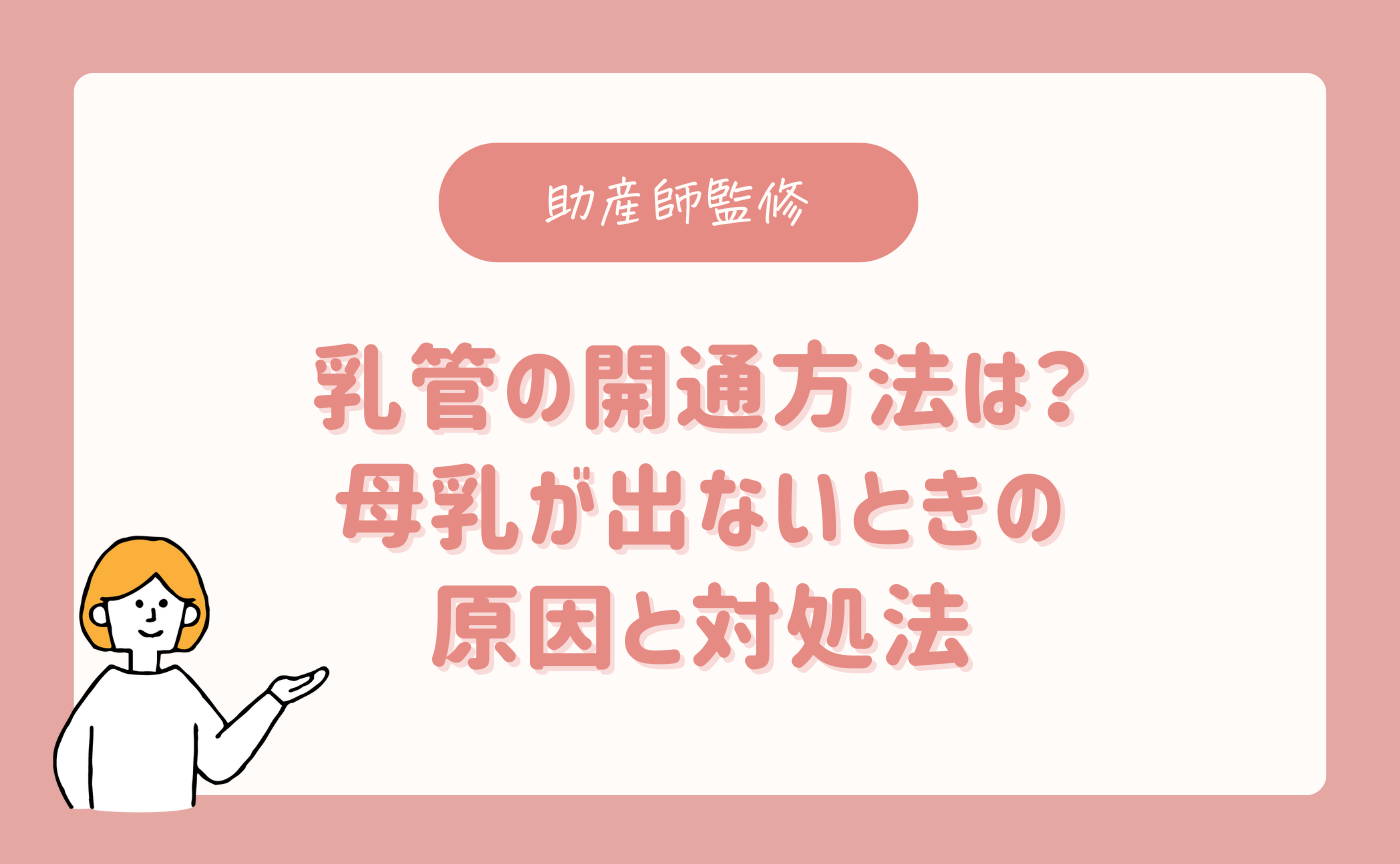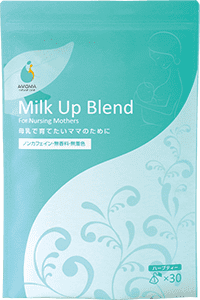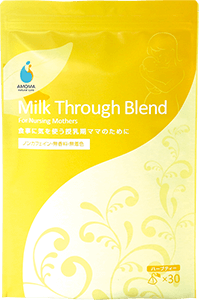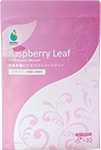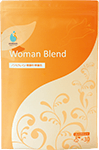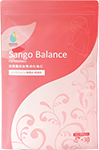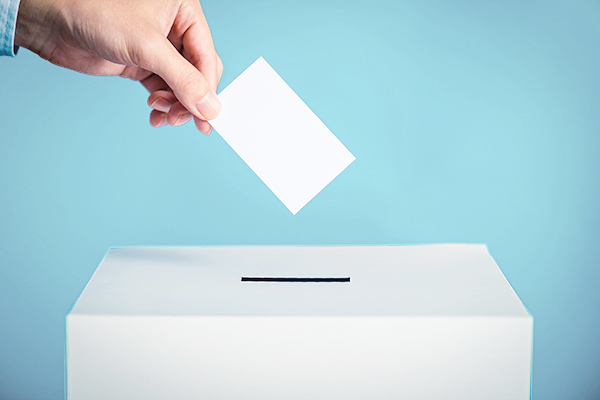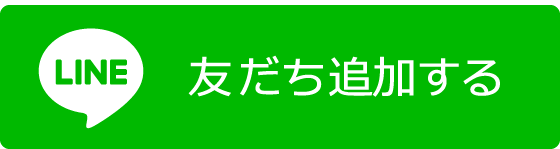【助産師監修】母乳の栄養はいつまで?母乳に含まれる栄養素とは?
2018.10.15

Yoneco Oda
Mama writer
2010年生まれと2016年生まれの姉妹を育児中のママです。おっとりマイペースな姉と、好奇心旺盛でパワフルな妹。姉妹でも性格の違う二人の様子に、子育ての新鮮さや面白さを感じている今日この頃です。

浅井貴子
助産師
新生児訪問指導歴約20年以上キャリアを持つ助産師。毎月30件、年間400件近い新生児訪問を行い、出産直後から3歳児の育児アドバイスや母乳育児指導を実施。
タグをみる
赤ちゃんにとって大切な食事である母乳。その母乳の成分や、含まれる栄養素はどのようなものか知っていますか?母乳の栄養素は、赤ちゃんの身体にどのような働きがあるのでしょうか。
また、赤ちゃんの月齢が進むと、母乳の栄養はなくなってしまうのでしょうか?
今回は、母乳の栄養はいつまで続くのか、母乳に含まれる栄養素を詳しく紹介します。
母乳の栄養素

たんぱく質
たんぱく質は、内蔵や血液などの、身体を作るための重要な栄養素の1つです。主に「ホエイ」と「カゼイン」に分かれます。
ホエイは初乳に多く含まれていて、赤ちゃんを風邪やアレルゲンから守り、免疫効果を高めるIgA抗体をたっぷりと含んでいます。カゼインは、乳汁に含まれるたんぱく質の一種です。
各種アミノ酸
アミノ酸は身体を作っていくためには欠かせない栄養素です。母乳には、体内では作り出すことができない必須アミノ酸のほか、豊富なアミノ酸がバランス良く含まれています。
各種ミネラル
母乳に含まれるミネラルには、カルシウム、りん、マグネシウム(鉄分)などがあり、骨や歯など身体の組織を構成しています。
母乳には赤ちゃんの身体に最適な量のミネラルがバランスよく含まれています。
各種ビタミン

母乳には、脳や体の成長に必要な葉酸などさまざまなビタミンが含まれています。
免疫力と抵抗力を高めるビタミンA、骨の成長に必要なカルシウムの吸収を助けてくれるビタミンD、抗酸化作用があるビタミンEなど。
ただし、出血を止めたり、骨を強くするために必要なビタミンKは母乳にあまり含まれていません。
そのため、赤ちゃんに1ヶ月検診時などにビタミンK2シロップを飲ませて不足を補い、ビタミンK欠乏性出血症を予防します。
脂質
母乳に含まれる脂肪は、赤ちゃんが動くための大切なエネルギー源となります。また、神経組織の発達やホルモンの生成に大事な役割をしています。
母乳は、授乳の飲み始めと飲み終わりで含まれる脂肪分の量が変わってきます。
飲み始めは薄く、脂肪分が少ないサラッとした状態ですが、だんだんと濃くなっていき、飲み終わり頃には3~5倍ほどの濃さになっていきます。
糖質

母乳の糖質は、主に乳糖です。乳糖はカルシウムの吸収を促し、体内のビフィズス菌を増やす働きもあります。また、脳の中枢神経系の発達にも欠かせない栄養素です。
また、赤ちゃんの腸内環境を健康的に保って、お通じをスムーズにしてくれるオリゴ糖も、母乳には含まれています。
母乳は全体の88%が水分でできているので、脱水症状を起こすなどの緊急の場合をのぞけば、離乳食前の赤ちゃんは母乳だけで十分な水分補給ができます。
このように、母乳には、赤ちゃんが健康に成長していくために必要な栄養素がたっぷりと含まれているので、赤ちゃんにとっての最高の食事といえますね。
母乳の成分は変化する

初乳→移行乳→成乳へ
出産後の数日間にでる乳汁は、どろっとしていて黄みがかっています。この母乳は、たんぱく質やミネラルなどの栄養や、免疫成分を豊富に含んだ特別な母乳で「初乳」と呼ばれます。
移行乳
産後5日頃から、母乳は量が増え始めて、色などの見た目、成分も変化していきます。
この時期の母乳は「移行乳」と呼ばれ、含まれる免疫成分やたんぱく質は減っていきますが、脂肪分や糖分が増加します。
成乳

産後10日〜2週間になると、白色でさらっとした感じの乳汁が分泌されるようになります。
この母乳は「成乳」と呼ばれ、初乳に比べると含まれる脂質、糖質が増えて、逆にたんぱく質とミネラルは減っていきます。
成乳はエネルギー消費の盛んな赤ちゃんに対応できるように、赤ちゃんの月齢や必要な栄養量に合わせて成分が変化していき、母乳の濃さもほぼ一定になります。
そして、これからの長期間に渡って、赤ちゃんの健康を支える大切な栄養源となるのです。
母乳の栄養はいつまで?

母乳はママの血液から作られています。ママが食べた食物からの栄養が血液となって、その血液は豊富な栄養を含んだまま母乳へと変ります。
そのため、生後6ヶ月経っても、1年経っていても、栄養素や免疫成分がなくなるということはありません。
しかし、赤ちゃんの成長の段階によって必要な栄養成分が変わってくるので、それに伴って母乳に含まれる成分も変わってくることがあります。
時間とともに減っていく栄養素もありますが、月齢が進むと赤ちゃんが量をたくさん飲めるようになるので、生後6ヶ月くらいまでは、おっぱいだけで必要な栄養の量をまかなうことができます。
離乳食のはじまり

体が大きくなり、運動量も増えてくると、たくさんのエネルギーが必要となります。
母乳やミルクだけでは、必要なエネルギーをまかなうことが難しくなってくるので、足りない栄養を補うために離乳食は始まります。
生後5~6ヶ月頃から離乳食をスタートする事が多いようですが、個人差があります。赤ちゃんの性格や様子を見ながら離乳食を開始してくださいね。
いかがでしたか。母乳には、赤ちゃんが健やかに成長するための大切な栄養素が、たくさん含まれています。また、その栄養素や免疫成分は、時間が経ってもなくなることはありません。
ママは、赤ちゃんに栄養価の高い母乳を与えられるように、栄養バランスの良い食事を摂るように心掛けましょうね。
【関連する記事】
【助産師監修】母乳の味は食べ物で変わる?おすすめの食事や控えた方がよい食べ物
【助産師監修】離乳食を食べない…上手な食べさせ方は?母乳だけで栄養は大丈夫?
関連記事
■体の悩み
-
 【医師監修】乳腺炎で発熱!病院に行くべき?症状・原因・対処法も詳しく解説2024.10.08
【医師監修】乳腺炎で発熱!病院に行くべき?症状・原因・対処法も詳しく解説2024.10.08 -
 【助産師監修】白斑があっても、授乳して大丈夫? 取り方などを紹介2024.10.08
【助産師監修】白斑があっても、授乳して大丈夫? 取り方などを紹介2024.10.08 -
 【助産師監修】生後1・2・3ヶ月ごとの授乳間隔・授乳回数の目安は?2024.09.17
【助産師監修】生後1・2・3ヶ月ごとの授乳間隔・授乳回数の目安は?2024.09.17
カテゴリーランキング
AMOMAコラムについて
妊娠、出産前後はママにとっては初めてのことばかり。「これってあってるのかな?」 「大丈夫かな?」と不安や疑問に思った時につい手に取りたくなるような情報をお届けしたいと考えています。そのため多くの情報は助産師をはじめ専門家の方々に監修。テーマから読めるようになっていますので、ぜひ気になるものから読んでみてください。あなたの不安や疑問が解決できるお手伝いになれば嬉しいです。
AMOMAのパートナー

看護師、助産師、IFAアロマセラピスト、JMHAメディカルハーバリスト、NCA日本コンディショニング協会認定トレーナー
母乳育児、新生児~幼児にかけての育児相談全般、アロマやハーブを使用した産前、産後ケア 代替療法全般

管理栄養士・幼児食アドバイザー
メンタルヘルス食カウンセリング、子供の心を育てる食育講座、企業向け健康経営セミナーなど

日本神経言語心理家族療法協会公認家族心理カウンセラー、NLPファミリーセラピー・マスタープラクティショナー、子どものこころのコーチング協会インストラクタ
心理カウンセラー

日本産婦人科学会会員その認定医、産婦人科専門医、日本ソフフロロジ学会会員、東京オペグループ会員、日本アロマテラピー学会会員
産婦人科医
その他のお問い合わせはこちらから
 メールで問い合わせ
メールで問い合わせ




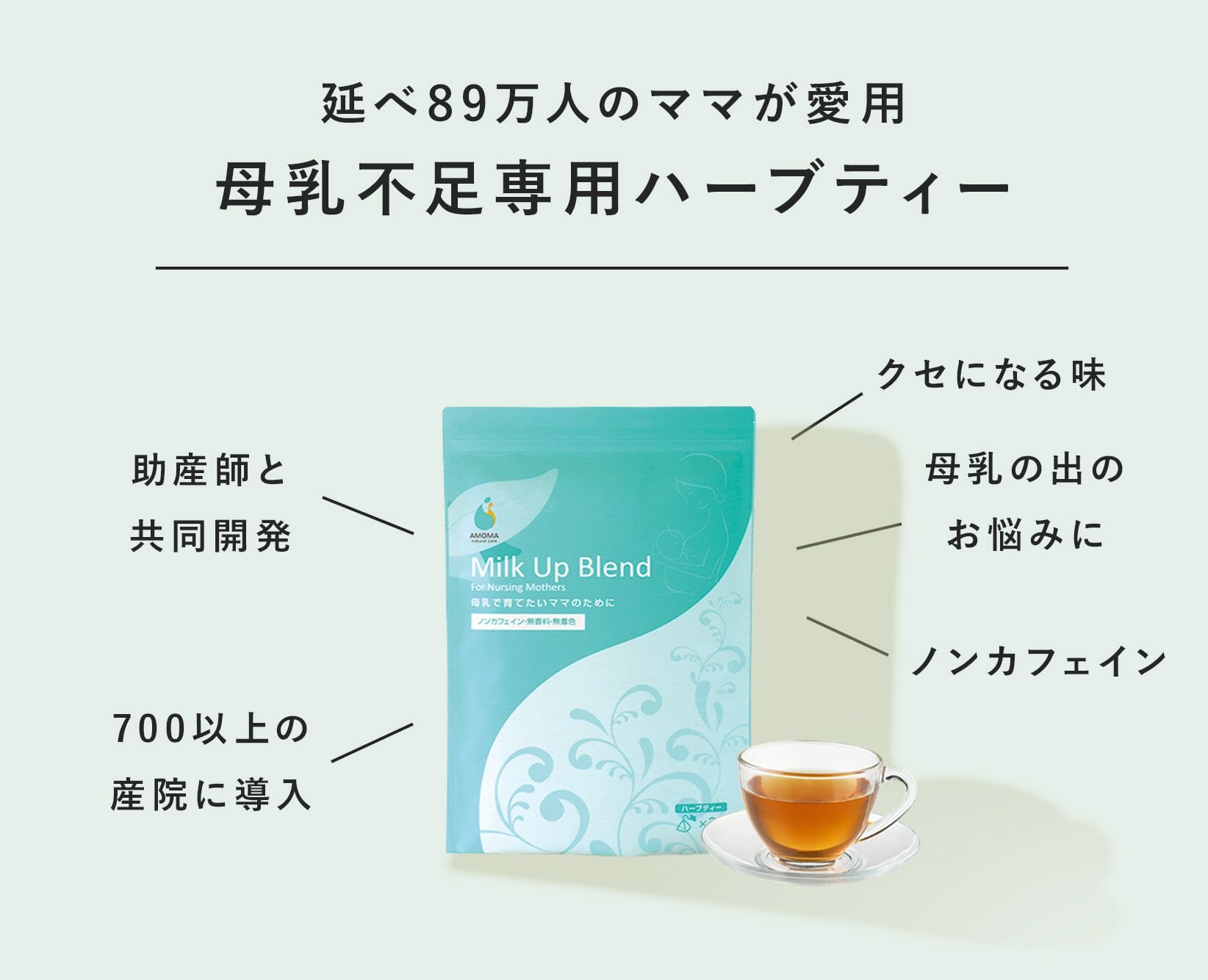
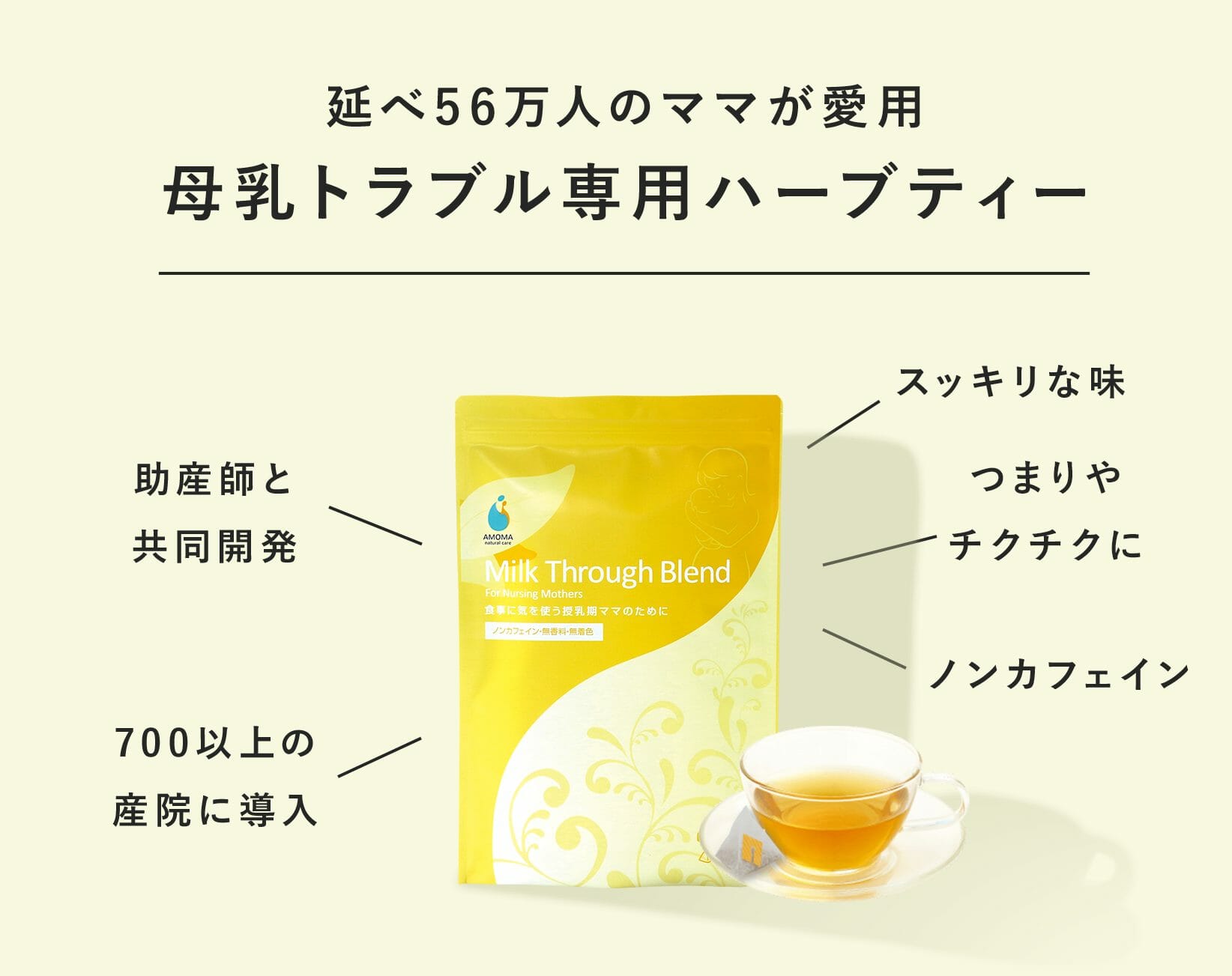

 amoma_naturalcare
amoma_naturalcare