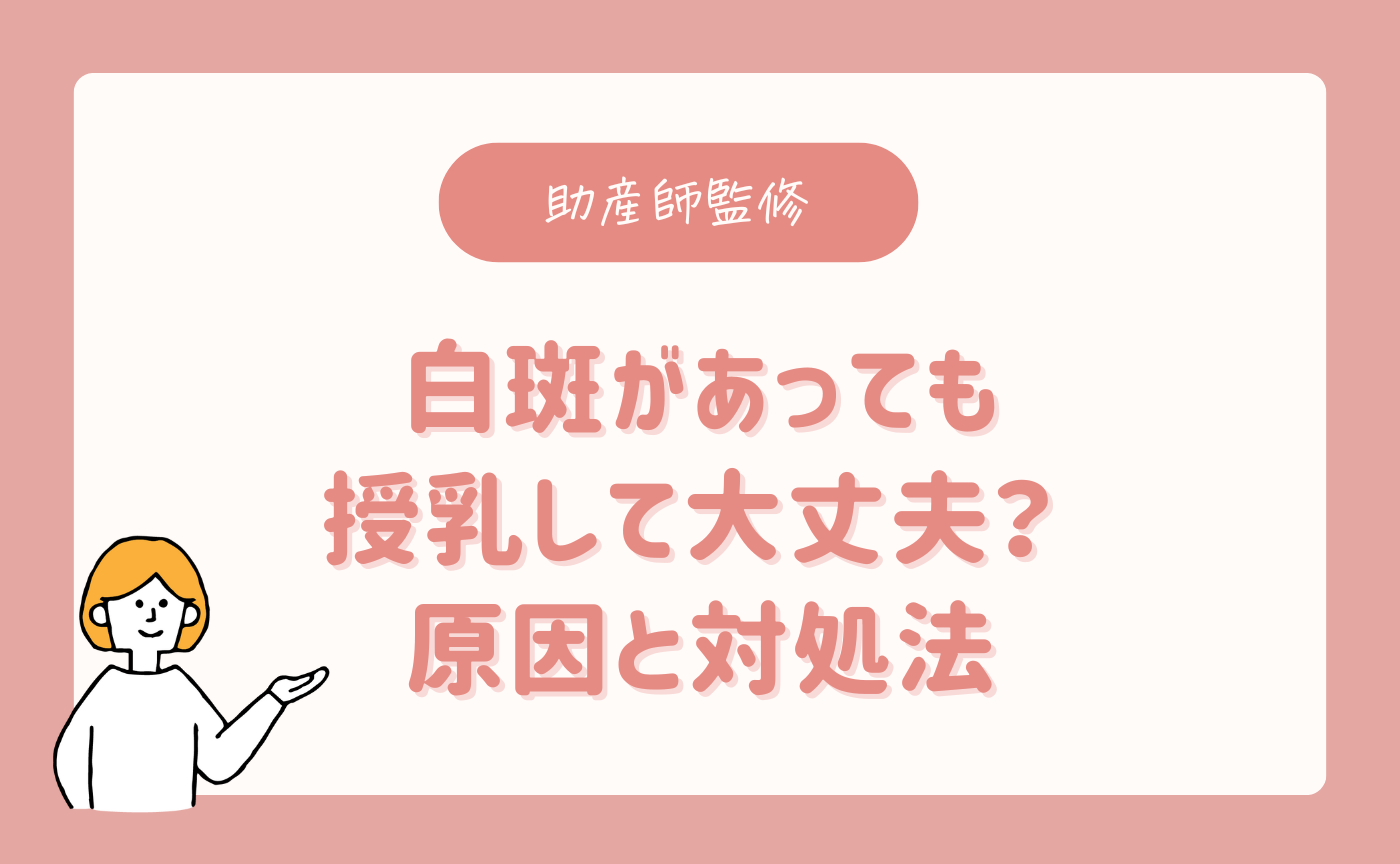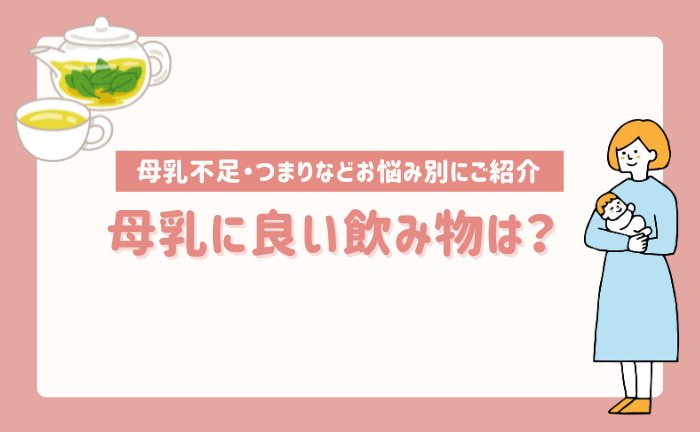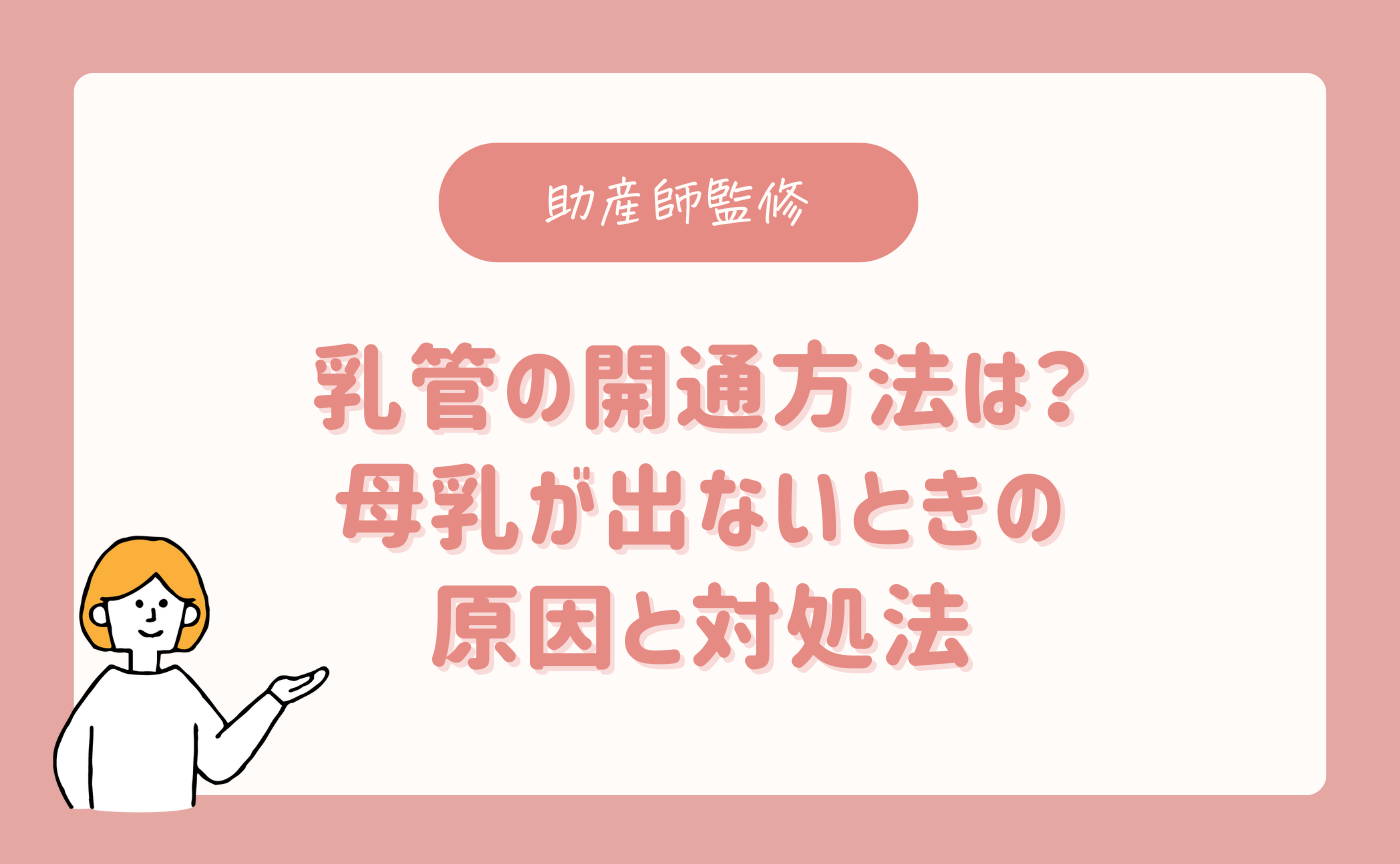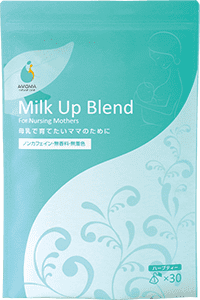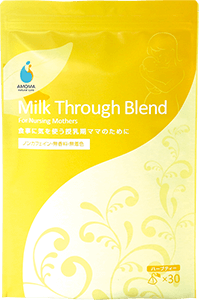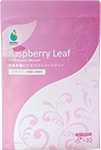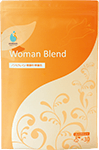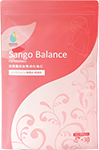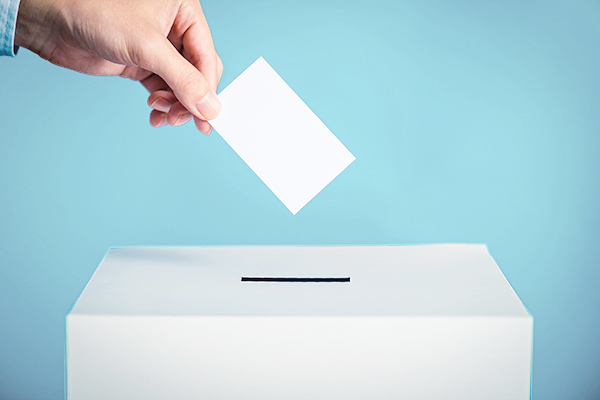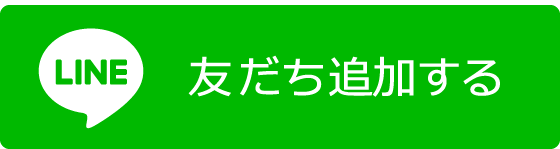【助産師監修】不妊の検査には何がある?種類や方法について
2019.02.06

ことまま
Mama writer
2017年1月生まれの女の子を育てている新米母です。夫は単身赴任なため、フルタイムで働きながら、ワンオペ育児に奮闘しています。育児疲れは仕事で癒し、仕事の疲れは娘の笑顔で癒しながら、毎日を乗り切っています。

浅井貴子
助産師
新生児訪問指導歴約20年以上キャリアを持つ助産師。毎月30件、年間400件近い新生児訪問を行い、出産直後から3歳児の育児アドバイスや母乳育児指導を実施。
タグをみる
思うように赤ちゃんが授からないとき、不妊外来など、婦人科の受診を検討するカップルが多いかと思います。でも、「なんだか怖そう」「どんな検査をするのか不安」と思ってしまうかもしれませんね。
今回は、不妊の検査にはどんな種類や方法があるかについてご紹介します。
不妊症かも、と思ったら

赤ちゃんがほしいと思うけれどなかなか授からないとき、『もしかして「不妊」なのかな?』という不安が頭をよぎるかもしれませんね。
最近ではドラマなどでも不妊について取り上げられ、身近な話題となりつつあるため、早く病院で検査してもらわなくては、と思う方も多いかと思います。
不妊の検査には、どのような検査があるのでしょうか?
不妊症の定義とは?

不妊とは
「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間妊娠しないものをいいます。
日本産科婦人科学会では、この「一定期間」について「1年というのが一般的である」と定義しています。
つまり、検査を受けなくても、妊娠を希望しながらも一定期間妊娠しなければ、「不妊症」といえます。
検査を受けるきっかけに

意外と厳しい基準ですよね。自分が当てはまる、とショックを受ける方もいるかもしれませんが、逆に言えば、自分の状況が把握できたということ。
そして、もし治療するのであれば、開始の早さは大切なポイントになります。「検査に行くきっかけができた」と前向きに考えてみてくださいね。
不妊症の6大基本検査

不妊症の検査には色々なものがありますが、以下に挙げるものは、一般的に「6大基本検査」と呼ばれ、ほとんどの医療機関で行われています。
基礎体温
専用の体温計を使います。毎日、起床時に布団の中で寝たまま測定し、基礎体温表などにグラフ化したものを、受診時に医師が確認します。
排卵や黄体機能不全の有無が分かる他、毎月のパターンから排卵日を予測したり、不正出血の原因を推測する手助けとなったりします。
頸管粘液検査
子宮の入り口である頸管部から粘液を採取し、量や粘り気、結晶が形成されているかをみる検査です。
頸管粘液は精子の通り道としての役割を持っており、少ないと精子が子宮に進入しにくくなります(子宮頸管粘液不全)。頸管粘液の量や性状から、卵胞の成熟度を推測することもできます。
フーナーテスト
排卵日頃の前夜あるいは朝に性交した後、注射器で頸管粘液を採取し、その中に精子が進入できているかを確認します。
進入した精子の運動性が高いか、数が多いかも確認します。運動性が高い精子がたくさん進入していれば、妊娠の可能性が高いと言えます。
子宮卵管造影
子宮の入り口から造影剤を注入し、X線を当てて、子宮の形に異常がないかや、卵管が通っているか、癒着がないかなどを調べる検査です。月経後に行います。
造影剤を通した後は卵管が拡張されるため、軽度の癒着が解消できる可能性があります。卵管の通りも良くなっているので、妊娠しやすい状態になっていることも多いようです。
経腟超音波検査
一般の婦人科でも行われるメジャーな検査で、内診と一緒に行われます。
固いものに当たると反射する超音波の性質を利用し、子宮内膜や卵胞をモニターに映し出します。膣内に親指程度の太さの装置を挿入して行います。
卵胞の成熟具合を確認できるほか、子宮筋腫や腺筋症、卵巣嚢腫などを見つけることもできます。
一般精液検査
これまで紹介した検査は、女性側が受ける検査でしたが、一般精液検査は男性側の検査となります。
実は、不妊原因のうち40%は男性側によるものといわれており、精液検査はとても重要な位置づけとなります。
精液を採取し、精子の数や運動状態、奇形がないかを顕微鏡で見ます。検査前には数日間の禁欲を指示されることが多いようです。
原因をつきとめて治療へ

病院や医師により、どの検査をどの程度重視するかは多少違いがあり、検査のメニューも変わってくるようです。6大基本検査の結果をふまえ、何が不妊の原因になっているかを突き止めていきます。
さらに、血液検査など、より詳しい追加検査に進むこともあります。検査の結果がそろったら、治療開始となります。
いかがでしたか。不妊の検査にはそれぞれにふさわしい時期がある為、複数回の通院が必要となります。また、パートナーの受診が望ましいとされる場合もあります。
実際に治療が始まった場合、通院する回数も増える為、ストレスなく通いやすい医療機関を選ぶことをおすすめします。
関連記事
■体の悩み
-
 【医師監修】乳腺炎で発熱!病院に行くべき?症状・原因・対処法も詳しく解説2024.10.08
【医師監修】乳腺炎で発熱!病院に行くべき?症状・原因・対処法も詳しく解説2024.10.08 -
 【助産師監修】白斑があっても、授乳して大丈夫? 取り方などを紹介2024.10.08
【助産師監修】白斑があっても、授乳して大丈夫? 取り方などを紹介2024.10.08 -
 【助産師監修】生後1・2・3ヶ月ごとの授乳間隔・授乳回数の目安は?2024.09.17
【助産師監修】生後1・2・3ヶ月ごとの授乳間隔・授乳回数の目安は?2024.09.17
カテゴリーランキング
AMOMAコラムについて
妊娠、出産前後はママにとっては初めてのことばかり。「これってあってるのかな?」 「大丈夫かな?」と不安や疑問に思った時につい手に取りたくなるような情報をお届けしたいと考えています。そのため多くの情報は助産師をはじめ専門家の方々に監修。テーマから読めるようになっていますので、ぜひ気になるものから読んでみてください。あなたの不安や疑問が解決できるお手伝いになれば嬉しいです。
AMOMAのパートナー

看護師、助産師、IFAアロマセラピスト、JMHAメディカルハーバリスト、NCA日本コンディショニング協会認定トレーナー
母乳育児、新生児~幼児にかけての育児相談全般、アロマやハーブを使用した産前、産後ケア 代替療法全般

管理栄養士・幼児食アドバイザー
メンタルヘルス食カウンセリング、子供の心を育てる食育講座、企業向け健康経営セミナーなど

日本神経言語心理家族療法協会公認家族心理カウンセラー、NLPファミリーセラピー・マスタープラクティショナー、子どものこころのコーチング協会インストラクタ
心理カウンセラー

日本産婦人科学会会員その認定医、産婦人科専門医、日本ソフフロロジ学会会員、東京オペグループ会員、日本アロマテラピー学会会員
産婦人科医
その他のお問い合わせはこちらから
 メールで問い合わせ
メールで問い合わせ




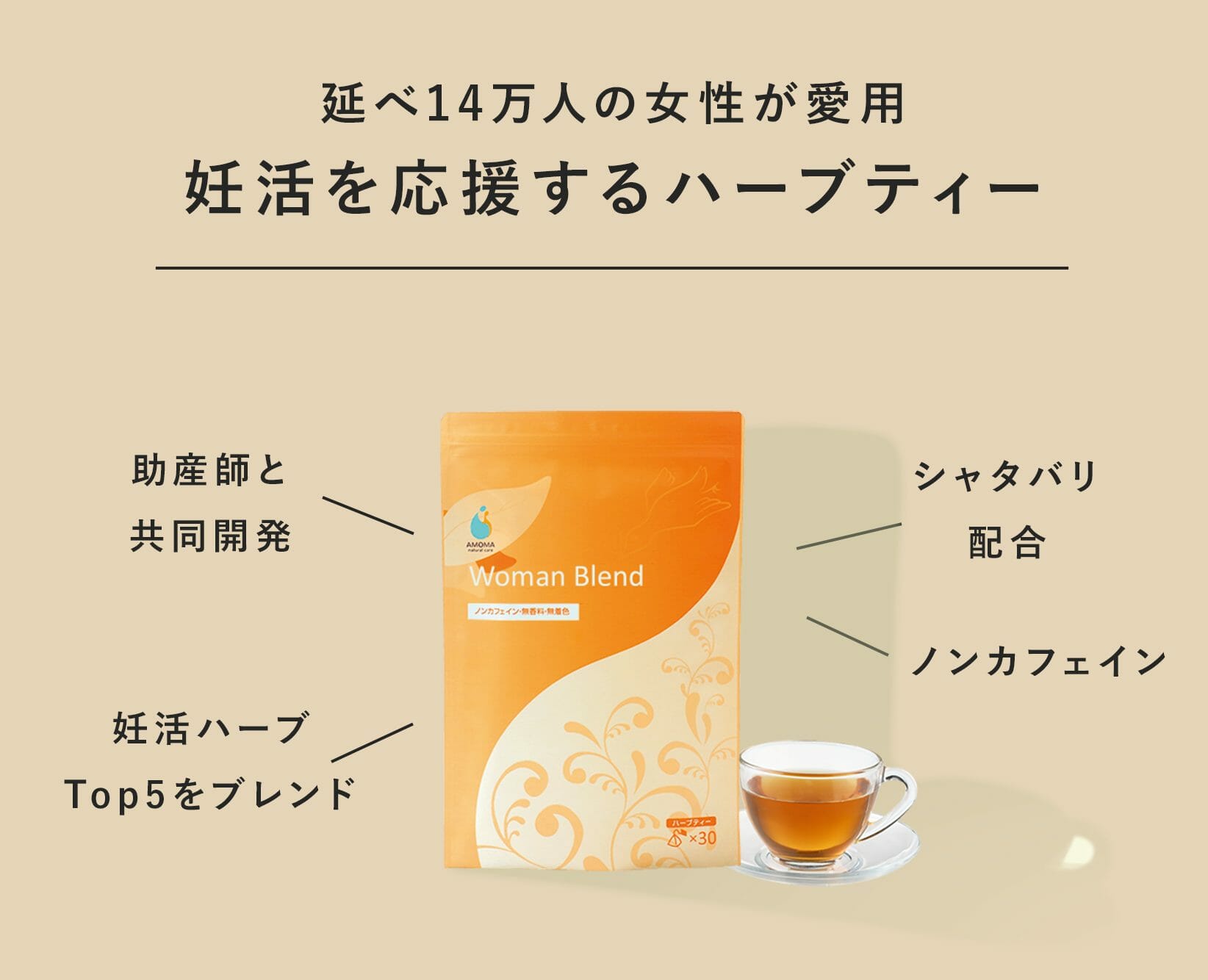


 amoma_naturalcare
amoma_naturalcare